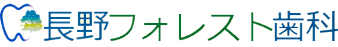こんにちは。長野フォレスト歯科の添野です。
新しい生活が始まる季節ですね。新たな気持ちでお過ごしの方もいらっしゃるかと思います。
慌ただしい日々かと思いますが、体調を崩さないようにしたいですね。
インプラントをお考えの方や、既にインプラントにされた方に知っていていただきたいのが、インプラントのお手入れについてです。
インプラントは「手術が終われば安心」という訳ではありません。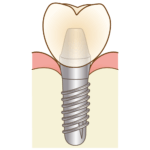
インプラントは、失った歯の機能を回復させる優れた治療法ですが、術後の手入れが非常に重要です。お手入れと寿命が直結します。
天然歯よりも入念なケアが必要とされるインプラントは、適切な清掃を行うことで長持ちし、健康な状態を維持することができます。
今回は、インプラントの日常での清掃方法と、歯科医院でのメンテナンスについて解説したいと思います。
インプラントは人工歯のため、実際むし歯にはなりません。むし歯にはなりませんが、インプラントを取り囲む歯ぐきや顎の骨は患者さんの生身の組織です。
インプラント周りの歯磨きや歯間清掃を怠ってしまうとインプラントと歯茎の境目の歯周ポケットに歯垢が溜まり、歯周病の一種である「インプラント周囲炎」を発症する可能性が高まります。このため、インプラントの治療後はインプラント周りを含めてしっかりと歯を磨くことが大切です。
目次
- 1 1.インプラントのお手入れを怠るとどうなる?
- 2 1−1 インプラント周囲粘膜炎
- 3 1−2 インプラント周囲炎
- 4 2.インプラントの清掃の重要性
- 5 2−1 インプラント周囲炎を防ぐため
- 6 2−2 長期的な成功率を高めるため
- 7 3.インプラントの日常での清掃方法
- 8 3−1 インプラント周りを入念に清掃する理由
- 9 3−2 毛先が細い歯ブラシ+通常の毛先の歯ブラシの2種類を使いましょう
- 10 3−3 歯間清掃も忘れずに行いましょう
- 11 3−4 デンタルフロス(糸ようじ)
- 12 3−5 ワンタフトブラシ
- 13 4.歯科医院でのメンテナンス
- 14 4−1 歯科医院での定期的で専門的なクリーニング
- 15 4-2 メンテナンスの内容
- 16 4−3 エアフロー
- 17 4−3−1 エアフローの特徴
- 18 4−3−2 エアフローの注意点
- 19 4-4 メンテナンスの周期
- 20 5.引っ越し等で歯科医院を変えるときの注意点
- 21 6.まとめ
1.インプラントのお手入れを怠るとどうなる?
1−1 インプラント周囲粘膜炎
インプラントのお手入れを怠ってしまうと、インプラントの周りにプラークが溜まり、そこに歯周病菌が増殖し、粘膜が炎症を起こしてしまいます。
天然歯のお手入れを怠ってしまう事で歯肉炎を起こすのと同じように、インプラントでもこのような炎症は起きてしまうので、毎日丁寧にケアする必要があります。
もし歯肉が腫れていたり、歯磨きの際に血が出る事があったら、インプラント周囲粘膜炎を起こしている可能性がありますので、気付いた段階で歯科医院で診てもらってください。
1−2 インプラント周囲炎
インプラント周囲炎というのは、インプラント周囲粘膜炎が進行し、炎症が骨にまで至ってしまった状況です。
歯周病が進行すると歯が抜けてしまうのと同じように、インプラント周囲炎を放置してしまうとインプラントが抜けてしまう事があります。
歯肉の腫れ、お痛み、出血、インプラントのぐらつきなどが、何か異変を感じた場合はすぐに歯科医院を受診し治療を受けてください。
またインプラント歯周炎は、進行するのが非常に速い点にも注意が必要です。これは一度かかると、歯周病の10~20倍の速さで悪化していくものと考えられています。こうした事情もまた、いざ気付いた頃には症状がかなり悪化しているといったことが起こりがちな要因だといえます。 インプラント歯周炎をしっかり予防するためにも丁寧なメンテナンスを心がけることが重要なのです。また万一こうした病気になった際に長期間放置してしまう事態を防ぐためにも、歯科医院での定期検診は大切なのです。
2.インプラントの清掃の重要性
2−1 インプラント周囲炎を防ぐため
インプラント周囲炎は、天然歯の歯周病と同じように歯茎に歯垢(プラーク)や歯石が残っていると、歯周病菌が増殖し、インプラントの周囲に炎症が生じます。放置すると歯周病菌が骨を溶かし、インプラントが不安定になったり、脱落したりする恐れがあります。
これを防ぐためには、日常的に徹底した清掃が不可欠です。
インプラント周囲の歯肉はデリケートなため、適切な清掃が健康維持の鍵となります。
インプラント治療後は、インプラント周囲炎という病気になる恐れがあります。インプラント周囲炎とは、口内が不衛生な状態になると引き起こされる細菌感染の一つで、インプラント周囲の歯茎や骨などに炎症が起こります。
歯茎の腫れや出血、重症化すると歯を支える歯槽骨と呼ばれる骨を溶かす症状が現れ、最悪の場合にはインプラントが抜け落ちることもあります。
2−2 長期的な成功率を高めるため
インプラントは、適切な手入れを行うことで長期間にわたり機能を維持することが可能です。
日々のケアを怠ると、インプラントの寿命が短くなり、再治療が必要になる可能性があります。
これを避けるためにも、適切な清掃を心掛けましょう。
3.インプラントの日常での清掃方法
インプラントの周囲を健康に保つためには、正しい歯磨き方法が不可欠です。
インプラントは通常の歯磨きと同じです。ただし、インプラント周りは入念に清掃しましょう。
インプラントに合わせた特殊な磨き方はありません。歯ブラシを45度の角度で歯肉にあて、優しく小刻みに動かして歯垢(プラーク)をしっかりと除去することが重要です。
また、電動歯ブラシを使用する場合も、同様の注意を払いながら丁寧に磨くことが大切です。
3−1 インプラント周りを入念に清掃する理由
インプラント周りの清掃を怠ると、インプラントと歯ぐきの境目の溝である歯周ポケットの中(アバットメント(連結部品)の周辺)に歯垢が付着し、歯周病の一種であるインプラント周囲炎を発症する可能性が高まります。
天然歯には、歯の根っこと骨の間に歯根膜という組織があります。歯根膜は血液を供給する役割を持っており、このおかげで虫歯菌や歯周病菌に対する抵抗力が保たれています。
しかし、フィクスチャーというネジのようなものを骨に直接埋め込むインプラントには、歯根膜がありません。その為、細菌に感染した場合の抵抗力が弱く、炎症を起こした場合は天然歯以上に進行が早いのです。歯を失ってしまった原因がむし歯や歯周病であった場合、その場所はお口の中でも特にお手入れが難しい場所だったという事になります。ですので、インプラントにされた場合は今まで以上に気を付けてお手入れをしてください。
インプラントと歯茎の境目や、隣の歯との間の部分、噛み合わせる面の凸凹した部分などは、特に気を付けて磨いてください。この時、しっかり磨こうと頑張り過ぎて、ゴシゴシと強く磨いてしまうとインプラントが傷付いてしまいます。
傷付いてしまうと、その傷に細菌が入り込んでしまうので、歯ブラシのブラシが潰れないくらいの強さで磨いて下さい。インプラント専用の歯ブラシも販売されています。
3−2 毛先が細い歯ブラシ+通常の毛先の歯ブラシの2種類を使いましょう
インプラント周りを清掃するときは、毛先が細い歯ブラシを使いましょう。毛先を歯周ポケットの中に入れ、人工歯の根本とアバットメント(連結部品)の周辺についた歯垢をかき出して落とすようにしてください。インプラント以外の天然歯についても同様に毛先を歯周ポケットの中に入れて歯の根面周辺についた歯垢をかき出しましょう。
しかし、毛先が細い歯ブラシは歯周ポケットに入りやすい反面、歯の表面の清掃力が落ちます。このため、歯みがきの際は歯周ポケット用の毛先が細い歯ブラシ(歯周病予防のために作られた毛先が細い歯ブラシがおすすめです)に加え、歯とインプラントの表面を磨くための通常の毛先の歯ブラシ(毛先が細すぎない通常の物)の2種類を使っていただければと思います。
3−3 歯間清掃も忘れずに行いましょう
インプラントの周囲の歯肉や歯の隙間を清潔に保つためには、デンタルフロスや歯間ブラシが有効です。
特に、インプラント専用のフロスを使用すると、細かい部分までしっかりと清掃することができます。
清掃時にはデンタルフロスでインプラントの側面(人工歯と隣の歯の隣接面)の歯垢を落としましょう。
歯間が空いている方は歯間ブラシを使ってもかまいません。ただし、無理に歯間ブラシを挿し入れるとインプラントや歯の表面を傷つけてしまうおそれがあります。歯間が狭い方は無理に歯間ブラシを使わず、デンタルフロスで歯間清掃を行ってください。
インプラントと隣の歯との間の部分は、歯ブラシだけではなかなか汚れは落とし切れません。歯間ブラシをお使い頂くと、より綺麗に細かい部分まで汚れを落とす事が出来ます。
インプラントだけでなく、隣り合っている歯を守る為にも、丁寧に磨いて下さい。
歯間ブラシには太さや硬さの種類がありますので、かかりつけの歯科医院で適したものを教えてもらうと安心です。歯間ブラシも強く磨き過ぎる事の無いよう、最初は歯科医院で使い方を確認してみて下さい。
3−4 デンタルフロス(糸ようじ)
歯間ブラシよりも細い為、歯間ブラシでは届き切らない場所の汚れも落とす事が出来ます。インプラントと歯茎の境目など、歯ブラシや歯間ブラシで磨けない部分を意識して使ってみて下さい。糸だけのものだと使いにくいという方は、持ち手の付いたホルダータイプのものをお使い頂くと良いでしょう。
3−5 ワンタフトブラシ
ワンタフトブラシとは毛先がペンのように尖り、束になった小さな歯ブラシです。
インプラント周りを清掃するときは、毛先が尖ったワンタフトブラシを使うことで人工歯の根本についた歯垢を落としやすくなります。
インプラント周囲や歯間の細かい部分にアクセスしやすく、通常の歯ブラシでは届きにくい場所までしっかりと清掃できます。
特に強い曲面のある奥歯のインプラントや、隙間が狭い部分には、ワンタフトブラシが役立ちます。
インプラントの周囲は天然歯に比べて汚れがたまりやすいです。
毎日、食後にしっかり清掃し、汚れをためないようにしましょう。
また、もし外出時で清掃が難しい場合でも口をゆすぐなどしてなるべくきれいに保つようにしましょう。
4.歯科医院でのメンテナンス
4−1 歯科医院での定期的で専門的なクリーニング
毎日きちんとお手入れをしていただいていても、磨き残しがあったり強く磨き過ぎているなど、正しくお手入れができているかどうかはなかなかご自身では気付けないものです。
歯科医院で定期的に受診していただくことで、その時に必要なことをアドバイスすることができます。
インプラントの周りの炎症や他の歯への影響、大切な噛み合わせの状態など、短いスパンで確認できればちょっとした異変にも気付くことができて、大事に至る前に治療を開始することができますので、歯科医院で指定された時期にはメンテナンスに足を運んでいただき、お口の中を健康に保って欲しいです。
歯科医院では、専門的な器具を使用して、日常の清掃では取り切れない歯垢(プラーク)や歯石を除去することができます。これにより、インプラント周囲の健康が保たれます。
・きちんとご家庭でお手入れしていただけているか
・インプラント歯周炎になっていないか
・噛み合わせがおかしくなっていないか
・人口歯がゆるくなっていないか
など、確認すべきことがたくさんあります。
4-2 メンテナンスの内容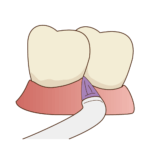
・レントゲン撮影
・お口の中全体の状態を確認
・クリーニング
・歯磨き指導 など
歯科医院によって頻度に差はありますが、定期的にレントゲンで骨の状態や歯の状態を確認します。
目視で確認できない骨などは、レントゲン撮影を行い確認します。インプラント治療では、インプラント体と呼ばれる人工歯根を顎の骨に埋め込むため、顎の骨に異常がないかどうかをチェックする必要があります。
インプラント周囲炎などが原因で顎の骨が溶けると、インプラントを支えきれなくなって抜け落ちることがあります。早い段階で発見することで、重症化を防げるでしょう。
また、レントゲン撮影は、歯と歯の間などの見えない場所のむし歯の確認にも役立ちます。
インプラントを長持ちさせるためには、インプラント自体のチェックはもちろん、全体的な噛み合わせを確認することも重要です。また、歯ぎしりなどの癖によって歯に負担がかかっていないかも確認します。
歯ぎしりや食いしばりなどの癖があれば、ナイトガードを製作するなど、歯を衝撃から守れるようにします。むし歯や歯周病があった場合は、治療を行います。強く噛み過ぎることで骨が減ってしまったり、天然歯への影響が見られる場合は、マウスピースの使用を勧められる場合があります。
また、お口の中全体の歯肉や歯の健康状態、噛み合わせの状態などを確認後、歯垢・歯石を専用の器具を使用し落とし、患者さん一人ひとりに合わせて、お口の中の状態に合わせた歯磨き指導を行うこともあります。歯の磨き方には癖があり、キレイに磨けていないところが存在しているケースも少なくありません。ブラッシング指導では、磨き残しの多い場所を教えてもらい、正しい磨き方を指導してもらえます。
歯ブラシ以外にも、デンタルフロスや歯間ブラシなどの使い方も教わることができます。セルフケアによるむし歯予防の効果をさらに高められるかと思います。
より健康的なお口になるためのアドバイスですので、ご家庭でのお手入れの際に取り入れていただけたらと思います。
定期メンテナンスでは、歯磨きだけは取り除けない汚れを専用の器具を使って除去します。
歯垢が付着した状態を放置すると、石灰化して歯石になります。歯石は、歯周病菌が増殖しやすい場所です。歯磨きでは除去できないため、定期的に歯科医院で除去してください。
セルフケアと併せて歯医者での定期的なクリーニングを受ければ、むし歯や歯周病を予防できる可能性が高まります。
4−3 エアフロー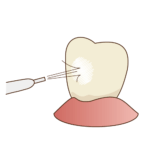
エアフローとは、専用の機器を使用して水と空気、細かいパウダーを噴射して吹き付けることで歯の表面をクリーニングする方法です。
当院では専用の器械を使い、エリスリトールという糖アルコールを原料としたパウダーと水流を使って歯の汚れや歯垢、バイオフィルムを除去し、インプラント体の周囲及び口腔全体のクリーニングをします。
インプラントは、歯の根を人工的に再現するもので、顎骨(がっこつ)に埋め込まれるチタン製のネジのような形状です。人工歯根と顎骨がしっかりと結合すれば歯根に連結部分を付け、人工歯冠を装着します。自立した人工歯根が人工歯を支える治療法であるため、隣接歯に負担を掛けるようなことはありません。入れ歯やブリッジと比べて、安定性や審美面は優れていますが、保険適用外であるため高価で手術が必要です。また、きちんと定期的にメンテナンスを行っていなければ、インプラントの周囲で歯周病のような炎症を引き起こし、ぐらぐらと動揺したり、外れる脱落を起こすことがあります。
エアフローの基本的な情報についてご紹介します。
4−3−1 エアフローの特徴
エアフローは細かなパウダーを用いるため、インプラント周囲のプラークやバイオフィルムを除去できます。バイオフィルムは1mgあたりにおよそ1億個の細菌がいると言われるため、それを放置しておくと歯周病や肺炎など全身疾患の原因になります。エアフロ―は従来のスケーリングよりも歯肉や歯に優しく、より綺麗にすることができます。主な特徴としては直接器機が歯肉や歯に触れるわけではないため、 短時間で痛みも少なく、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)やステイン(着色汚れ)、早期の歯石などを効果的に除去できます。
インプラント周囲の清掃でエアフローを使用すれば、デリケートな部分を傷つけることなく汚れを取り除けます。定期的にエアフロ―によるクリーニングでメンテナンスを続けると、インプラント周囲の炎症や感染を防げ、インプラントの寿命をより長く延ばせます。エアフローは短時間で処置が完了するため、患者さんにとって負担が少ない方法です。歯茎の健康を保つことができ、歯茎の炎症を防ぎ、全体的な口腔内の健康を維持することができます。
・細かいパウダーは体に優しい成分
エアフロ―で吹き付ける細かいパウダー具体的に挙げると、糖アルコールのエリスリトールを主成分とした水溶性のパウダーです。糖アルコールは歯垢を分解しやすくなる作用があるため、それを歯面に吹き付けて水流をかけることで綺麗な歯になります。当院では取り扱っておりませんが炭酸水素ナトリウムを主成分としているパウダーもあり、糖アルコールや炭酸水素ナトリウム(重曹)はいずれも体に優しい成分になります。
・高い清掃効果
歯周ポケットの清掃においては、スケーラーの器具では届かない深さまでアプローチ出来るのがエアフロ―です。より確実に歯周病を予防できます。また、頑固な着色汚れやヤニもしっかり落とすことができます。
・スピーディー
細かい部分まで効率的にクリーニング出来るため、スケーリングと比べて、お口を開ける時間が、短時間で済みます。
・歯にやさしい
ジェット水流と微粒子のパウダーを使用するため、従来の研磨剤による「擦り落とすクリーニング」に比べて歯や人工歯を傷つけにくく、優しくクリーニングができます。
・歯石が着きにくくなる
クリーニング後は歯の表面がツルツルになるため、歯石や着色の再付着の予防になります。
4−3−2 エアフローの注意点
エアフローの注意点としては使用頻度でしょう。インプラントを長持ちさせるためのおすすめする頻度(通院間隔)は、約3~6ヶ月に一度の間隔でエアフローを行いましょう。エアフローは、プロである国家資格を持った歯科衛生士による施術を受けることがとても重要です。自己流で勝手に行ってしまうと、インプラントや歯茎にダメージを与えてしまい、口腔機能が更に悪化する可能性があります。
インプラント手術を行った後に長持ちさせるためには、適切なメンテナンスが不可欠です。エアフローは痛みが少なく、短時間でインプラント周囲を効果的に清掃する方法として非常に有効です。定期的なエアフローの使用と、日常的な口腔ケアをしっかり行うことで、インプラントの寿命を延ばし、健康な口腔環境を維持することができます。エアフローによるメンテナンスを取り入れて、インプラントを長く快適に使用しましょう。
4-4 メンテナンスの周期
インプラント治療後の定期メンテナンスの頻度は、一般的に3ヶ月〜6ヶ月に一回程度です。頻度は患者さんのお口の中の状態や、歯科医院によって異なります。
ご自身で不具合などを感じていらっしゃらない場合、メンテナンスに行くことは面倒かと思いますが、不具合が出てからでは治療が困難になることもあります。
メンテナンスは必ず受けていただき、インプラントもご自身の歯も健康に保っていただければと思います。
5.引っ越し等で歯科医院を変えるときの注意点
10年、20年とインプラントを機能させるために大切なメンテナンスですが、中には引っ越しによってインプラント治療を受けた歯科医院への通院が難しくなったり、病院そのものが閉院してしまう可能性もあります。
しかし、現状では他院での治療には対応していない歯科医院も多いのです。
またインプラント治療は行っているものの、他院で埋入したインプラントのメンテナンスは対応しない歯科医院は少なくありません。
また、インプラントの再治療は通常のインプラント治療よりも難度が上がり、どこの歯科医院でもできるわけではありません。
「インプラント治療をしている=メンテナンスや再治療を受け入れてくれる」というのは誤りです。
しかし、インプラントメーカーによって判断される可能性もごく僅かですがあります。
インプラントには多種多用のメーカーがあり、世界中で100種類以上、日本国内では30種類以上が使用されています。
メーカーによって、部品の規格や装着用ネジの種類などは異なるため、このメーカーのインプラントなら対応するけれど、このインプラントには対応していないなど、使用しているインプラントが同じ場合の転院のみ受け入れる歯科医院もあります。
何らかの事情で遠方への引っ越しを余儀なくされた場合、転居先での新しい歯科医院でも定期検診等のアフターケアを続けていくためにはなにに注意すればよいのでしょうか。
まずはこうした引っ越しに際して、ご自身で使用しているインプラントを製造しているメーカーや、そのインプラントの種類などについてはきちんと把握しておきましょう。そのインプラントに対する治療や各種検診に対応してもらえる病院を探すために必要な情報であるからです。
6.まとめ 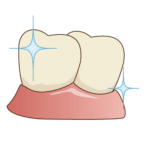
見た目が美しく噛む感覚も損なわないインプラントには、多くのメリットがあります。
しかし、定期メンテナンスやセルフケアを怠れば、インプラント周囲炎になるリスクが高まります。トラブルが起こった際の負担が増加することもあるかと思います。
インプラントはきちんとしたお手入れをしないと細菌感染などのリスクも高く、インプラントを外さなければならない状態や抜けてしまった場合には、同じ場所に再度インプラントを埋め込むことは難しくなります。
正しい方法で丁寧にお手入れをして頂き、メンテナンスに通って頂ければ、10年以上もしくはそれ以上の長い期間お使いいただくことができます。
口腔内の汚れを歯磨きだけでキレイに落とすことはとても難しいです。そのため、定期メンテナンスでプロのクリーニングを受けて汚れを徹底的に除去し、インプラント周囲炎の原因となる細菌の繁殖を抑え、発症を予防することが大切なのです。
また、インプラント周囲炎は自覚症状がないことが多く、インプラント治療をした歯は他の健康な歯に比べて細菌への抵抗力が低いです。
気づいたときには症状が進行している恐れがあるので、定期的なメンテナンスで早期発見することが重要です。
日々のブラッシングをはじめとするセルフケアはもちろんのこと、専門の歯科医師による定期検診などは、たとえ転勤などで住む場所やライフスタイルが大きく変わることがあったとしても一生涯続けていくようにしましょう。
毎日のお手入れで、インプラントを快適にお使いいただき、残っていらっしゃるご自身の歯の健康も守っていきましょう。